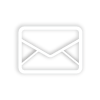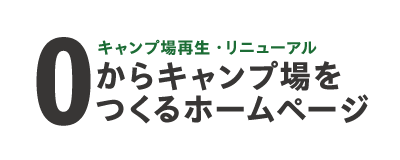アウトドアプロデューサー
松山拓也

日本のキャンプ場の歴史とニーズの変遷から考える
「キャンプ」と聞いて、皆さんはどんな風景を思い浮かべるでしょうか?
自然の中でテントを張り、焚き火を囲みながら過ごす穏やかな時間。あるいは、ボーイスカウトや林間学校のような、集団での野外活動を思い出す方もいるかもしれません。
日本におけるキャンプ文化は、時代とともに大きくその姿を変えてきました。いま求められているキャンプ場とは、どのようなものなのでしょうか?その答えを探るために、まずはその歴史を振り返ってみましょう。

キャンプの原点 ― 野営としての歴史
そもそも「キャンプ(野営)」という行為は、はるか昔、狩猟時代の移動生活や、戦時下における兵士の宿泊手段として、ごく当たり前に行われていたものです。日本で近代的なキャンプが行われたのは明治・大正時代。
1916年には、現在の滋賀県・琵琶湖畔で、日本初のボーイスカウトによる野営が実施され、その記念碑が今も残されています。
当時のキャンプは、いわゆるサバイバルや教育的活動の一環。衣食住すべてを野外で行い、ゴミ捨て場や仮設トイレも自分たちで作るという、非常に実践的かつ原始的な体験でした。現代の感覚からすると、想像しにくい不便さだったかもしれません。
集団訓練的キャンプとアウトドアカルチャーの違い
キャンプの歴史をたどる中で見えてくるのは、「集団訓練型キャンプ」と「アウトドアカルチャーとしてのキャンプ」という、2つの大きな流れです。
集団訓練的キャンプとは
戦争や教育的背景を持ち、集団行動や規律を学ぶことを目的としたキャンプスタイルです。昭和期の林間学校や宿泊訓練などがその典型例で、団体生活を通して自立や協調性を育むことが主眼に置かれていました。
アウトドアカルチャーとしてのキャンプとは
一方で近年広がってきたのが、自然との共生を楽しむライフスタイルとしてのキャンプです。
人が自然と向き合い、四季折々の景色や静けさを味わいながら、自然の中でゆったりと過ごす、このような価値観が、多くの人に支持されるようになりました。
現代は、かつての「集団・統一」の時代から、「個性・多様性」の時代へと移り変わりました。キャンプもその例外ではありません。一人ひとりが自分のスタイルで自然と向き合い、ルールとマナーを守りながら、より文化的にキャンプを楽しむ時代へと変化しているのです。

アウトドアの登場がもたらした価値観の転換
1970年代、日本でも「アウトドア」という概念が登場し、従来の価値観を大きく変えていきます。これは、ベトナム戦争後のアメリカ社会の変化や、環境保護の機運の高まりとも深く関係しています。
それまで人類は、科学や機械の力で自然を制御・開発することに価値を見出してきました。しかしその結果、自然破壊が進んだことを受け、次第に「自然を守る」「共に生きる」という発想が広がっていきました。世界遺産として自然が保護され始めたのもこの頃です。
アウトドアは、自然にできるだけ負荷をかけず、そこにある美しさを尊重しながら時間を過ごすライフスタイル。現代では、パタゴニア社に代表されるように、環境保護とアウトドアカルチャーが強く結びついています。

昭和のキャンプと現代のキャンパーの意識
昭和の時代、日本のキャンプは教育の一環として団体行動を前提に設計されていました。林間学校、宿泊訓練、野外炊飯など、ある意味「試練」を通して人間的成長を目指す場でもありました。
しかし令和の今、そのような訓練的なキャンプを望む人は多くありません。現代のキャンパーは、豊かな自然の中で、自分らしい時間を過ごすことを求めています。

キャンプ場の稼働率が示す“価値の変化”
実際、キャンプ場の稼働率にもこの意識の変化は顕著に表れています。稼働率の低いキャンプ場の多くは、訓練型の設計を色濃く残しており、現代のニーズとズレがあることが原因と考えられます。
一方、SNSなどで注目を集める人気のキャンプ場は、広々とした区画、静かで景観の良いロケーション、プライベート感のある空間といった特徴を備えており、「快適で、自然を感じられる場所」が評価されているのです。

これからのキャンプ場づくりに必要なこと
今後、新しくキャンプ場を作る、あるいは既存の施設をリニューアルする際に最も重要なのは、「どんな体験をお客様に提供するのか」という明確なビジョンです。
そのビジョンは、立地条件や自然環境によってさまざまです。海の見える丘、川のせせらぎ、森の静寂。どんな場所にも、そこにしかない魅力があります。それをどう切り取り、どう伝えていくかが問われます。
今、求められているキャンプ場とは、「快適さ」と「自然との一体感」を両立させ、訪れる人一人ひとりが自分の時間を豊かに過ごせる場所。
ルールとマナーの中で、多様なスタイルのキャンプが尊重され、文化として成熟していく、そんな未来が、これからのキャンプカルチャーには求められているのです。